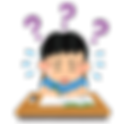検索結果
空の検索で131件の結果が見つかりました。
- 今年もみんなで七夕飾り!
< Back 今年もみんなで七夕飾り! ブ ロ グ 2025年7月22日 短冊がいっぱい! 今年もみんなで七夕飾りを行いました! あまり飾りつけを作れず最初は少しさみしい感じだったのですが、 短冊を書いて・・・、 短冊を書いて・・・、 みんなで飾っていくと・・・、 最後には短冊だらけになっていました! 願い事も多岐にわたっており、 学校で起きてほしいこと、習い事の上達に関するもの、お家のこと、など 色んな内容を思い思い書いていました。 子供たちにとって楽しいイベントになっていれば何よりです! 今後も季節ごとに子供たちが楽しめるイベントを用意していきたいと思います! お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール : gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 100%理解できないとダメ? | 学童塾KASICO
< Back 100%理解できないとダメ? コ ラ ム 2023年12月11日 完璧に理解しないと先に進めない子供 勉強は 100 %完璧に理解しないとダメ なものなのでしょうか? 誤解を与えてしまうようなタイトルですが、 理解せずに勉強しろという意味ではありません 。 むしろ、理解は大事ですし、何も考えずに機械的にやっていくことは、先に進むにつれ躓く原因にもなってしまいます。 今回お伝えしたいのは、 100 %理解しないと手や頭が全く動かなくなる、という状態になるぐらいなら、 「完璧には分からないけど、習った通りにやったら一応できるから、とりあえずこれで進めよう」 という、難しい課題に対する心の態度の話 をしています。 こんな話をするのは、 高校レベルになるといきなり 100% 完璧に理解するというのはほぼ不可能 だからです。 塾講師時代の話になりますが、 数学を教えているとまったく手の動かない子が一定数存在 しました。 やり方も教えて、その通りにやればできるのになぜ手を動かさないのか聞いてみると、 「よくわからないから」 と口々にいます。 考えれば当たり前の話なのですが、 高校レベルになるとかなり抽象的な内容も含みだすので、具体的なものとしていきなりすべてを理解するというのはほぼ不可能 です。 こういった 抽象的なものはやっていくうちに、「あっ、そういうことか」となってわかってくる ものがほとんどです。(複素数平面、微分積分、帰納法、ユークリッド互除法、量子力学など) かくいう私も、小学生時代「きはじ」(きょり・はやさ・じかん)を習ったとき正直あまりよくわかっていませんでした。 ただ教わった通りにやっていると答えとしてはそれらしいものが出てくるので、とりあえずこれで進めておこうとそのまま取り組んでいました。 そのまま使い続けて 1 年ほどたつと理解が深まり、 「ああ、あれはこういうことだったのか」と得心がいった ことを覚えています。 この時の体験から、数学に対しては、 「最初は何となくしかわからないけど、やっているとそのうちわかってくるはず」 と考えて取り組むようになったことを覚えています。 要は、 よくわからなくて気持ち悪いというストレスを飲み込んで先に進む強さもいずれ必要 になってくるということです。 お子様に対しては、 「完璧に理解しないと先に進んではダメ!」と過度に求めず、「いつかは理解するだろう」と長い目で見守ってあげていただきたい なと思います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール :gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 早期の英語教育はプラス? | 学童塾KASICO
小学校低学年からの英語学習は本当に必要か?多くの受験生を見てきた経験から言える、英語よりも優先して身につけるべき「強固な日本語力(思考の土台)」の重要性。 < Back 早期の英語教育はプラス? コ ラ ム 2021年12月15日 大学受験の英語には日本語力がマスト? 近年、英語教育が小学校で義務化されるなど英語の早期学習が叫ばれていますが、 早く学べば学ぶほど大学受験に有利となるかと言われれば正直かなり疑問です。 これまで英語を中心に難関大を目指す学生に指導をしてきましたが、 英語で詰まる人のほとんどは日本語で詰まっている という印象です。 大学受験で出される英語の問題はすべて和訳できたとしても、正直大人が読んでも難しいような内容となっています。 特に英文和訳は例え単語の意味が分かって日本語を並べたとしても、 それが日本語として正しい言い回しか自分で判断できずに間違っている生徒がほとんどです。 小さいころに英語を学ぶ時間があるなら、 読書をしたり、正しい言葉で会話をしたり、論理的思考力を鍛えるゲーム をしたりする方がよっぽど将来の英語力に寄与すると考えています。 当塾では単語を組み合わせて文を作る論理ゲームなどを行い、正しい日本語となっているか自分で判断できるよう子供たちの成長をサポートしていきます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール :gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 早期英語教育について | 学童塾KASICO
< Back 早期英語教育について コ ラ ム 2024年10月31日 早期英語教育について 近年、小学校低学年から英語教育が始まり、懇談中にも「英語を早く習ったほうがいいでしょうか?」とよく質問を受けます。 確かに小学校で必修化・教科化したこともあり、中学校に入るまでにある程度単語を覚えておかないと困るところもあると思います。 ただ、私としては大学入試や社会人として使うことを目的とした場合、 そこまで 急いで英語を習う必要性は感じておりません。 以前のコラム 「早期の英語教育はプラス?」 でも触れたことがありますが、 大学受験指導をしていて、 英語で躓く子のほとんどが日本語力の不足から来ている と感じることが多くありました。 和訳した自分の日本語の意味が通るか判断がついていない子、 日本語から主語、述語、目的語、副詞などの品詞の関係をきちんととらえられず英訳で苦戦する子、 など、様々なパターンがありましたが、 いずれも 日本語力の不足が根本 にある問題でした。 特に難しい大学になればなるほど、和訳、英訳、読解がメインになり、 その文の内容は日本人が日本語で読んでも複雑なものがほとんどで、単に英語の単語や意味が分かっても理解できない内容や問題が非常に多くなってきます。 学年や志望校のレベルが上がるにつれ、 英語の偏差値を上げるためには日本語のしっかりした力(土台)が不可欠 です。 さらに、 早期の英語学習(英語漬けの生活)は、逆効果になる ことも示唆されています。 カミンズ(Cummins, 1984)によると、トロントに移住した日本人を10年間追跡した調査の結果、 どの年齢で移住しても日常会話レベルの習得には大きな差がない一方、 幼少期(6歳まで)に移住した子ども は、学習言語力(英語読解力)を身につけるのに長い時間がかかり、小学校3年生の頃には学校の勉強についていけなくなる傾向があることがわかりました。 逆に、 小学校3年生以降に移住した子ども たちは、最初は苦戦しても最終的には難しい内容を理解し、現地の学校の勉強にもきちんと適応する傾向が見られました。 もちろん、こちらの研究がすべてだとは思いませんが、 私の塾講師時代の経験に照らしても納得できる部分が多く、 私たち 日本人が思考する際に用いるのは日本語 なので、 日本語を高いレベルで習熟し、その使い回しに熟達していないと、 論理的に考えたり、難しい内容をかみ砕いて理解することに非常な困難が伴うことは想像に難くありません。 したがって、 英語学習を始める前に日本語の土台がしっかりできているということが何よりも大事 であると考えています。 「仕事で使うために話せるようになっておいたほうがいいのでは?」とお思いの方も多いと思いますが、 学生の頃に数か月留学をしたり、社会人になって1年ほど勉強するだけで、あっという間に英語を仕事レベルで使えるようになった人を何人も見てきました。 (高校卒業レベルのある程度の基礎があれば、大体の人が日常会話レベルはすぐに話せるようになるイメージがあります。) 英語が必修・教科化したからといってあまり焦られず、 お子様の成長に合わせて冷静に検討していただきたいなと思います 。 Cummins, J. (1984). Wanted: A theoretical framework for relating language proficiency to academic achievement among bilingual students. In C. Rivera (Ed.), Language proficiency and academic achievement (pp. 2-19). Clevedon, UK: Multilingual Matters. ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール : gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 【2022年度】夏休みの新規受付の休止について | 学童塾KASICO
< Back 【2022年度】夏休みの新規受付の休止について 重要 2022年6月16日 【2022年度】夏休みの新規受付の休止について 学童塾KASICOで夏休みのご利用をご検討くださりありがとうございます。 大変恐縮ですが、現在 夏休み枠が少なく なってきたため、 夏休みのみのお申し込みについては現在休止 しております。 ( 平常も併せてご希望のお客様については、引き続きご案内 いたしております。) 空き状況が確定しましたらこちらにて再度案内を開始する予定ですが、再開時期については現在のところ未定です。 わかり次第こちらにてご案内いたします。 【補足】 ・6月17日時点で説明会をお申し込みの方については、夏休みのみのご利用も対応しております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール :gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 新1年生の登室が始まりました!
< Back 新1年生の登室が始まりました! ブ ロ グ 2023年4月3日 新1年生をみんなで歓迎! 本日4月3日より新1年生の登室が始まりました。 みなさま最初は新しい環境で慣れない様子でしたが、 いろんな遊びを通じて1日過ごすことで、だんだんと教室になじんできた感じがしております。 上級生の子も歓迎ムードでお出迎えです。 新1年生用の図書などを集めた専用の席も用意しています。 ACTやパズルプリントを通じて花びらシールを集めて楽しんでいます。 春休みは定員に達しておりますが、 平常でのご利用は現在も募集中 です。 「KASICOでどんなことをしているか 少し興味がある 。」 という方は、お話を聞いてみるというだけでも全然大丈夫ですので、 右下の説明会リンクよりお気軽にお問い合わせください! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール : gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- どこまでが親の責任?(その2) | 学童塾KASICO
< Back どこまでが親の責任?(その2) コ ラ ム 2022年12月23日 子供の面倒ってどこまで見るべき? 前回のコラム 「どこまでが親の責任?(その1)」 で、子供に任せることの大事さについて触れました。 明日の学校の準備 宿題の確認と完了チェック 子供の荷物の片づけと持ち運び 忘れ物チェック ・ ・ ・ など、いろいろある中で、具体的にどこまでを子供の責任として任せるべきなのでしょうか。 私の考える判断の仕方は、 「その行為の最終的な結末を引き受けるのはだれか」 ということです。 これが 「親」であれば、親の責任 ですし、 「子供」であれば、子供の責任 と考えています。 一例をあげてみましょう。 例えば、 「宿題」をしないことによる最終的な結末 は誰が引き受けるのでしょうか。 もちろん学校で怒られたり、勉強についていけなくなったりするという点で、 「子供」 です。 こういった課題には、 親であっても安易に踏み込まない ということが大事です。 アドラー心理学ではこれを 「課題の分離」 としています。 成功も失敗も、子供自身が選択し、その結末を引き受けることで、反省が生まれ、次のステップに進むことができます。 これを親が代わりに引きうけてしまうと、 子供自身で「考え、判断し、実行し、反省し、改善する」 という大事な成長の機会を親自身が奪ってしまうことになります。 もちろん子供が主体者となり、親を頼った場合においては、 フォローやアドバイスを与えたりすることは全く問題ありません 。 ただ、どこまでいっても、サポートはできるが、 強制をしたり、失敗を代わりに引き受けることはできない ということです。 お子様の成長を信じ、乗り越えるのを待つ姿勢 こそ必要なのかもしれません。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール :gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 算数の読解について(令和6年度全国学力調査より) | 学童塾KASICO
< Back 算数の読解について(令和6年度全国学力調査より) コ ラ ム 2024年9月24日 必要な思考の癖 表題の問題ですが、こちらは全国の小学校6年生が解いた令和6年度の全国学力調査の問題です。 少し読んで答えを考えてみます。 答えは、もちろん「ア」の「72+28」です。 こちらの 問題の正答率が、62.3% (私としては、結構ショッキングでした・・・。) 間違いのほとんどが「イ」の「72-28」を選択しており、 問題文の「少ない」という言葉から短絡的に「引き算」を選んで解答したことが推測されます。 子供からは「ちゃんと読んでなかった」「ケアレスミスだった」という声が聞こえてきそうですが、 私はそうは思っていなく、むしろ文章題の問題を解くときに 悪い癖がついている ために起きていることだと考えています。 最初に皆様に問題を読んで答えを考えてもらいましたが、 大人であれば、無意識に問題文を読みながら、ゆうまさんとこはるさんをイメージして折り紙の保有状況を 頭の中で図式化 して、答えを導いていると思います。 私もそうでしたが、算数や数学の文章問題を解くときは、必ずと言っていいほど落書きのような絵を書きながら考えていました。 子供たちはこの「図式化」の作業がまだ自然にできませ ん。 だからこそ、算数の文章題では問題を読むだけでなく、 絵を描きながら考える習慣をつける ことがとても大切です。 (当学童塾でも論理クイズのなかでこういった問題がたくさん出てきますが、お家で算数の問題を一緒に考えるときにも絵を書いてあげて、図で考える癖がつくよう時間をとってあげていただけたらなと考えています。) また、「少ない」という言葉から「引き算」と 短絡的に解答をしてしまっている思考パターン にも懸念を感じています。 問題を解いているときに、 「本当にこんなに簡単か?」「問題なんだから少しはひねりがあるんじゃないか?」 という問いを自分に投げかける力がまだ十分に育っていない ためであると考えています。 ひっかかって悔しい思いを重ねていけば少なくなっていくとは思いますが、 基本的に大学入試などは、短絡的には解けないものがほとんどなので、 「本当にそうか?」とスタートする前に一旦立ち止まる思考の癖 は非常に重視しています。 こういった思考の癖は、なぞなぞやひっかけのクイズなどで、楽しみながら身についたりすることもあるので、興味がありそうでしたらお家で遊んでみるのも一つだと思います。 本コラムが皆様の参考になれば幸いです。 [参考文献] 文部科学省・国立教育政策研究所. "令和6年度 全国学力・学習状況調査 報告書(算数)". https://www.nier.go.jp/24chousakekkahoukoku/report/24report/index.html 教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査」 https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.h ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール : gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- どこまでが親の責任?(その1) | 学童塾KASICO
< Back どこまでが親の責任?(その1) コ ラ ム 2022年12月5日 子供の面倒ってどこまで見るべき? 「子供の世話は親の仕事。わたしがしっかり面倒見なくちゃ」 そう思っている方は非常に多いと思います。 ただいったい どこまでが親が面倒を見るべき範囲 なのでしょうか。 例えば、 明日の学校の準備 宿題の確認と完了チェック 子供の荷物の片づけと持ち運び 忘れ物チェック ・ ・ ・ などなど、子供が小学生になるとやることも増え、悩んでいる方も多いと思います。 私が保護者様とお子様の関係を見ている中で言えるのは、 「子供の面倒を見すぎると 子供の自立が妨げられる 」 ということです。 一例をあげてみましょう。 例えば、明日の学校の準備を親が確認している場合、 その上で、子供が忘れ物をしたとしましょう。 その時、子供は学校でどんな気持ちになるでしょうか。 自分が忘れ物をしたことを反省するでしょうか? 「お母さんのせいで学校で困ったじゃん!」 「なんでちゃんとチェックしてくれなかったんだ!」 「お母さんしっかりしてよ!」 ・ ・ ・ と、まず間違いなく、忘れ物をきちんとチェックしてくれなかった 親のことを恨みます 。 学校で 困るのは子供自身 にもかかわらず、なぜか 親の責任 になってしまいます。 これでは自らの課題を自分で責任を持って考え、行動し、反省し、改善していく “自立心”を持った人間 に成長していくかは甚だ疑問です。 これまで大学受験指導をしてきて、 成績が目覚ましく伸びるのは、“自立心”を持った子供 がほとんどでした。 「そうはいっても子供に任せるにはまだ難しい」 「子供が困るのは、かわいそうだ」 と、お思いの方もいらっしゃるかもしれません。 そのお気持ちは非常によくわかります。 もちろんすべて子供に任せてやらせればいいというわけではありません。 時にはアドバイスをし、フォローしてあげることも大事です。 ただ、子供は皆様が思ってらっしゃる以上に成長しているものです。 任せてみると案外うまくやるかもしれませんし、失敗し悩むかもしれません。 ただそれを 乗り越えていくのを見守って、サポート してあげる。 そう信じて待ってあげる姿勢も大事だと考えています。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール :gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 子供がミスをしたとき | 学童塾KASICO
計算ミスを叱っていませんか?ミスを責められた子供は、失敗を避けるために「何もしない(挑戦しない)」ことを選びます。能力を伸ばすために親がすべきなのは、叱責ではなく「信頼して待つ」こと。 < Back 子供がミスをしたとき コ ラ ム 2023年10月30日 子供のミスにどう反応していますか? 先日夜道を帰っていた時の話なのですが、 習い事の帰り?らしき女の子(3年生ぐらい?)とそのお母さんが、 一緒に夜道を帰っているところと遭遇しました。 その娘さんは激しく泣いており、隣でお母さんは、 「なんであんな計算でミスしたの!家での練習をサボってたんでしょ!」 と激しい剣幕で怒っていて、 女の子は、 「ごめんなさい・・・、ごめんなさい・・・」と泣きながら謝っていました。 他人には察せられない深い事情があったのかもしれませんが、 私は何とも言えない思いを抱きながら近くを通り過ぎました。 ミスを攻めれば、子供は今後ミスに対して気を付けるのでしょうか。 親からの叱責を避けるために、 子供にとって一番合理的にミスをなくす方法は 注意して問題を解くことや練習すること、 ではありません。 もっと楽な方法があります。 それは、 「何もしないこと」 です。 間違える可能性がありそうな問題は、最初からチャレンジしたりしなければミスなどは起こらないのです。 前の塾でもそうでしたが、残念ながらそういった生徒は、一定数存在しました。 (いわゆる無気力症、アドラー心理学でいう「無能の証明」のような状態になっています。) 能力を伸ばすためには、 自分のレベルよりも少し高い問題にチャレンジし続ける必要 があります。 その際 「ミスしたらどうしよう」という迷いは、チャレンジする際の足かせ になってしまします。 受験期直前に点数効率を高めるために、自ら進んでミスに気を付けるのは全く問題ないのですが、 本来励ましてくれる存在であるべき身近な人にそれを強要されるのは、少し酷だなと感じてしまいます。 大人でもミスをしますし、ましてやまだまだ未熟な子供です。 お子様を信頼して成長を待ってあげる姿勢こそ必要 なのかもしれません。 (具体的な対応などはまた別のコラムで紹介したいと思います。) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール : gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 夏休みのご利用ありがとうございました!
< Back 夏休みのご利用ありがとうございました! ブ ロ グ 2022年9月15日 夏休みのご利用ありがとうございました! 夏休みも無事終わりました! 最初から最後まで多くの方に楽しく過ごしていただけてうれしく思います! 少し遅くなりましたが、これからのご利用をご検討されている方の参考になるよう、 このページでは夏休みの様子を振り返ってみたいと思います! (※お子様の写真を載せられないので、作品や記録が中心となります。) 【ラキュー作品】 最も遊ばれていたのがLaQでした! 最初のほうは平面しか作れなかった子も夏休みが終わるころには、立体の作品を作るなど、目に見えて空間認知のスキルが上がっていっていました。 またコマを作って回したり、ごっこ遊びをするなど想像力を使っていろんな遊び方で楽しんでいました。 【KASICOグランプリ】 LaQの次に遊ばれていたのが、パズルや集団ACTをクリアしてもらえるシール集めでした。 多くの子がこういったパズルに没頭して、たくさんの問題を解いていました。 小学校1年生のお子様でもどんどん解いていく様は見ていて「すごいなぁ」と感心させられました! 【ご利用者様の夏休みのご感想】 夏休み終了後に保護者様からアンケートをいただいています。 「とても満足」 と 「やや満足」 を合わせると 100%! 「とても満足」 だけでも 80%以上 と多くの方からご好評いただきました。 本当にありがたいことだと思っております。 さらにご満足いただけるようサービスとシステムの拡充をより一層進めていきます! 最後に保護者様からのコメントを一部抜粋して記載いたします。 ご検討中の方のご参考になれば幸いです。 <保護者様のコメント> ・カシコでみんなと遊べるのを楽しみにしていました。行かない日も行きたいと言っていました。 ・学童の中で勉強も教えていただけるところ。特に日頃学校や家では勉強したことがない、ACTなどがあり、子供の新たな一面をみることができました。 ・毎日の日中の様子、ACTに取り組んでる様子をLINEで教えてくださるので、帰ってから子供と一緒に話ができ楽しかったです。 ・子供の興味をそそって、遊びながら思考力を鍛えるACTを提供してくれることです。 ・カシコくなっている感じがします。満足です。 ・クイズや謎解きなど以前とは違うことに子供か興味を持つようになりました。 ・いろいろな本が読めるので、知識を深めているようです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― お問い合わせは下記までお気軽に! ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール :gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
- 勉強は親が教えたほうがいい? | 学童塾KASICO
< Back 勉強は親が教えたほうがいい? コ ラ ム 2022年3月31日 教えることは難しい 勉強に関する相談で、「勉強は親が教えたほうがいいのか?」と聞かれることがあります。 お子様が勉強をやっている様子を見ると、ついついやり方や答えを教えてあげたくなるものです。 しかし、 “やる気を奪わず” に勉強を教えるというのは非常に難しいものです。 よくある失敗例を以下に書いてみます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 子供:「うーん・・・」 (算数の文章題を悩んでいる様子) 親:(すごく簡単そうな問題で悩んでいるな。よしいっちょやり方を教えてやるか) 親:「すごく簡単な問題じゃないか。どこがわからないんだ?」 (子供に近づいて、問題を指さしながら) 子供:「?? ええっと・・ここなんだけど。」 親:「ほら問題にこう書いてるでしょ?だから、ここをこうやって、こう考えて・・・。ほら、答えが出たでしょ?こうやってやったらいいんだよ。」 子供:「こうかな?」 親:「ちがうちがう。さっきもいったじゃん。ここはこうやるんだよ。ね?簡単でしょ?」 子供:「・・・。」 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 親からすると親切心で解き方を教えてあげてるだけかもしれません。 ただこのやり方は勉強に対する子供のやる気と興味を一瞬にして奪い去る可能性があります。 皆さんも悩んで苦労してわかったものやできたものに対しては、少なからず喜びや達成感を感じるのではないでしょうか? 子供に“近道”を教えるということは、小さいことながらもその経験を奪ってしまうということにつながります。 これでは、自分で試行錯誤して問題を解決していく楽しみを見出せるはずがありません。 このように育ったことどもは勉強に興味を持たないばかりか、悩んだときは「答えを誰かが教えてくれる」という非常に受け身な子供に育ってしまう危険性さえはらんでいます。 では、どのように接すればいいのでしょうか? 親と子供の関係性やお子様の学年にもよるとは思いますが、 “一緒に悩む” というスタンスがやりやすいかもしれません。 たとえばこんな感じです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 子供:「うーん・・・」 (算数の文章題を悩んでいる様子) 親:(問題で悩んでいるな。よし、少し一緒に考えてみるか) 親:「おもしろそうな問題だね。どのへんで悩んでる?」 子供:「うーん・・。ここなんだけど・・・。」 親:「うーんたしかにここは難しいな・・。こんなことやってるなんてすごいな。」 子供:「ここまではいけてそうなんだけどなぁ。」 親:「そうなんだ。この辺がポイントなんかな?うーん、お父さん(お母さん)でもよくわからないわぁ。むしろできたらやり方を教えてほしいな。」 (ヒントらしきものを示唆しながら。) 子供:「・・・。もう少しやってみる。」 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― どうでしょうか? このあとお子さんは問題が解けず放置してしまうかもしれませんが、それはそれでいいのです。 大事なのは ”自分の頭を使って考えること” と、 ”勉強への興味を失わない” ようにしてもらうことなのです。 子供は意外とタフで一度投げたように見える問題でも目に付く場所などに置いていると、再チャレンジしてすらすらと解いてしまったりするものです。 そうした経験が子供の大きな自信となり、その後の “生きる力” となります。 親の “子供を信じて見守る姿勢” がなにより大事なのです。 ちなみに私の親は小学校のころから算数の問題を聞きに行くと答えはいつも悩んだ挙句「さっぱりわからん」でした(笑) 学童塾KASICOでは、上記のような姿勢で子供たちに接するよう心がけています。 また、こういった内容の具体的なご相談にも対応しております。 お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ・事業所名:学童塾KASICO(がくどうじゅくかしこ) ・事業内容:岡山市(北区)にて「学童保育+塾」で子供が賢く育つサポートをしております ・所在地 :〒700-0817 岡山県岡山市北区弓ノ町2-9 弓ノ町ビル201 ※岡山中央小学校徒歩1分 ・電話番号:086-238-6094 ・メール :gakudojuku@kasicojuku.com Previous Next
%20(1).png)